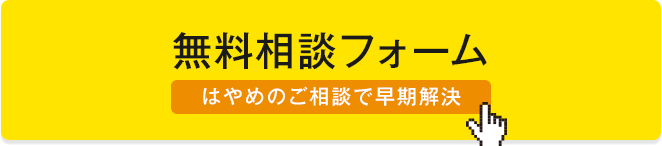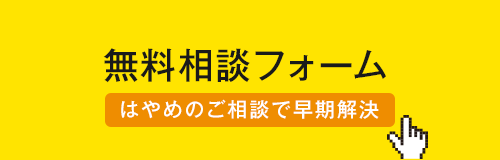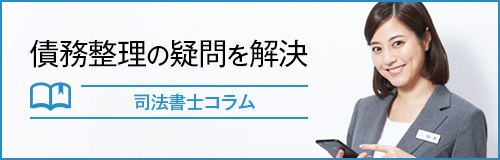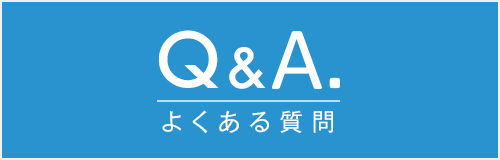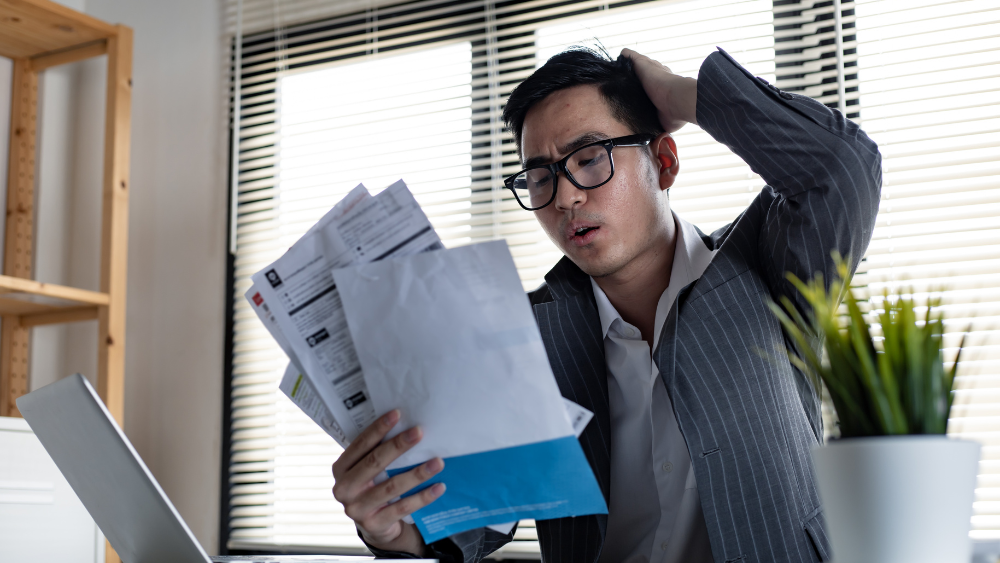2025.06.02
債務整理
受任通知とは?その効力と注意点を解説

借金の返済が滞り、金融会社からの督促や取り立てが続いて、精神的に追い込まれるケースも少なくありません。職場にまで電話が来るようになると、仕事も手につかない状態に陥りかねません。そのような状態から抜け出す解決策として、債務整理があり、認定司法書士が間に入ることにより、速やかに督促や取り立てを止めることができます。
その際に送付される「受任通知」とは、弁護士や司法書士などの専門家が依頼を受けた際に、依頼者から正式に受任したことを相手方に通知する文書です。この通知は、法的な手続きや交渉が、代理人となる専門家を通じて行われることを明確にし、相手方である債権者に対して重要な意味を持ちます。
この記事では、受任通知の概要とその効力、さらに注意すべきポイントについて詳しく解説します。
受任通知とは?基本の意味と役割

受任通知の法的な意味とは?
受任通知は、司法書士が依頼を受けた際に、依頼者に対して「この案件を受けました」ということを正式に伝えるための重要な書類です。依頼者にとっては、依頼が適切に受け付けられた証拠となり、また、関係者に対しても自分がその案件を取り扱っていることを通知する意味があります。受任通知は単なる連絡の一環として使われるだけでなく、法的にも重要な役割を果たします。
1. 受任通知の基本的な意味
受任通知は、司法書士が依頼を受けて業務を開始する際に、その事実を依頼者に正式に通知するものです。この通知をもって、依頼者との契約が成立したことになります。依頼者にとっては、自分の問題が適切に処理されることへの安心感を得ることができる重要な書類です。
2. 受任通知が果たす法的な役割
・依頼の正式な証明
受任通知は、依頼者と司法書士との間で正式に契約が結ばれた証拠となります。この通知により、司法書士がその案件に関して法的な代理権を持つことが確認されます。
・第三者への通知
受任通知は、第三者(例えば、債権者や他の関係者)に対して、司法書士がその案件を取り扱っていることを通知する役割もあります。これにより、第三者は直接依頼者に連絡を取るのではなく、司法書士を通じてやり取りを行うことが期待されます。
・法的責任の確認
受任通知を出すことで、司法書士はその案件に対して法的な責任を負うことになります。依頼を受けた時点で、司法書士はその案件に対する業務を遂行する義務を負うことになります。
3. 受任通知の内容
・依頼者の名前や住所
依頼者の基本情報が明記され、誰からの依頼を受けたかがはっきりと記載されます。
・案件の概要
どのような業務を受けたのか、その概要が簡潔に示されます。例えば、債務整理、相続手続き、登記申請など、具体的な業務内容が書かれます。
・業務開始の日時
受任通知には、業務が開始された日付も記載されます。この日付が、司法書士が正式にその案件を取り扱い始めた日となります。
・相手方への通知
必要に応じて、相手方(例えば、債権者)への通知が記載されることもあります。これにより、相手方は司法書士に連絡を取るべきことが通知されます。
4. 受任通知を送付するタイミング
受任通知は、業務を開始した直後に送付されることが一般的です。依頼者が法的手続きを求めている場合、早急に通知を送ることで、依頼者が安心できるとともに、案件に対して司法書士が責任を持って取り組んでいることが明確になります。
受任通知は、依頼者と司法書士の間で正式に契約が結ばれたことを証明する重要な書類です。また、第三者に対しても司法書士がその案件を取り扱っていることを通知する役割があり、法的に責任を負うことを確認する意味もあります。
受任通知が送られる背景(債務整理、専門家の介入など)
受任通知は、司法書士や弁護士が依頼を正式に受けた際に、相手方に対して「自分が代理人としてその案件を取り扱うことを通知する書類」です。この通知は、主に債務整理や法的な交渉が始まったことを示す重要な書類であり、特に債務者の立場においては、取引のあった金融機関や貸金業者などからの督促や取り立てが一時的にストップする可能性があります。
1. 債務整理の依頼を受けた場合
債務整理の手続きを依頼された場合、司法書士や弁護士が金融機関など債権者に対し、受任通知を送ることがあります。債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産などがありますが、いずれの場合も、受任通知を送ることにより、依頼者に対する債権者の取り立て行為を一時的に停止させることが可能です。
【債務整理の流れ】
1.依頼者からの相談: まず、債務整理を希望する依頼者から相談を受けます。
2.受任通知の送付: 依頼者に代わり、債権者に対して受任通知を送付します。これにより、債権者は司法書士または弁護士を通じて交渉することとなります。
3.取り立ての停止: 受任通知が送られることで、債権者は法的に依頼者への直接的な取り立てをすることができなくなります。
受任通知によって、取り立てを止めなければいけないことは、貸金業法の21条1項に定められています。もし法律に違反して取り立てや督促を行った場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、若しくはその両方の刑罰を科すものと定められています。
場合によっては、業務停止命令や貸金業登録取消などの行政処分を受けることもあります。一般的な金融会社であれば、受任通知を受け取った後に、取り立てや督促を行うことはありません。
2. 弁護士や司法書士の介入を通知する
弁護士や司法書士などの専門家が債務整理の代理人として介入した場合、それを通知するための書類である「受任通知」は非常に重要な役割を果たします。専門家が介入することにより、債権者は依頼者と直接交渉することができなくなり、弁護士や司法書士など、「代理人となった専門家」を通じて交渉が進められます。
【弁護士介入の効果】
・交渉の専門性: 弁護士や司法書士は法律の専門家として、債権者との交渉を効果的に行い、最適な解決策を提案します。
・法律的保護: 依頼者が借金問題を解決するための強力な法的なバックアップが得られます。
・借金の軽減: 弁護士や司法書士は、債務額の削減や支払い条件の変更などを交渉し、依頼者の生活再建をサポートします。
3. 受任通知の役割と重要性
受任通知は単に債権者に代理人を知らせるだけでなく、依頼者を法的に保護するための手段でもあります。特に、債務整理においては、以下のような役割があります。
・取り立ての停止: 受任通知が送られると、債権者からの電話や書面による取り立てが止まり、依頼者は精神的な負担を軽減できます。
・法的な交渉のスタート: 司法書士や弁護士が代理人として交渉を始めることにより、依頼者は自分の権利を守りながら問題解決に向かうことができます。
・正式な手続きの開始: 受任通知は、債務整理などの手続きが正式に始まったことを示すものであり、依頼者にとって重要な一歩となります。
4. 受任通知送付後の流れ
受任通知が送られた後、債務整理は次のステップに進みます。具体的な手続きは、依頼者の状況に応じて異なりますが、債権者との交渉が進み、最終的な解決方法が決定されます。
【受任通知送付後のステップ】
・任意整理: 利息を減額し、分割払いの交渉を行います。
・個人再生: 裁判所を通じて、一定額の債務を減額し、再生計画を立てます。
・自己破産: 法的に破産を申請し、残りの債務を免除されることを目指します。
受任通知は、債権者からの取り立てを止め、適切な手続きを進めるために必要不可欠な通知です。
借金の督促が止まる「受任通知」が送られるまで
借金の督促が続くと、毎日のように電話や手紙で精神的に追い詰められることがあります。そのような状況から解放されるために有効な手段が、司法書士などの専門家に依頼して送られる「受任通知」です。受任通知が送られることで、借金の督促が一時的に停止し、依頼者は精神的な負担から解放されるとともに、今後の対策を専門家とともに計画的に進めることができます。
受任通知とは、司法書士や弁護士が借金問題の解決を依頼された際に、債権者に対して送る文書です。この通知によって、専門家が依頼者の代理人となり、債権者との交渉を行うことを正式に伝えます。
1. 受任通知が送られるまでの流れ
まず、弁護士や認定司法書士に相談をし、債務整理の方針を決定します。その後、正式に「受任契約」を結び、各金融会社に「受任通知」という書面を送ります。受任通知とは、弁護士や認定司法書士などの専門家が依頼者から債務整理の依頼を受けた旨を通知する文書で、受任通知を受け取った金融会社は、訪問や電話・書面など一切の取り立てや督促はできなくなります。
同時に、返済が一時中断しますので、債務整理の手続きが完了し、返済が再開されるまでの間に生活再建の準備を行います。
1.相談・依頼
借金の督促に悩む依頼者が、司法書士に相談をします。依頼者は、借金の額や債権者、支払いの状況など、必要な情報を提供します。
2.必要書類の確認
司法書士は、依頼者から提供された情報をもとに、借金の詳細を確認します。債務内容や契約書、督促の履歴などを整理し、必要な書類を集めます。
3.受任通知の作成
司法書士は、依頼者を代表して受任通知を作成します。受任通知には、依頼者が正式に代理人を立てたことや、今後の連絡先(司法書士事務所)が記載されます。
4.債権者への送付
受任通知は、債権者(銀行や消費者金融など)に郵送されます。この通知が届くと、債権者は依頼者への直接的な督促を停止し、今後は司法書士を通じての連絡となります。
2. 受任通知の役割とメリット
受任通知が送られることには、いくつかの大きなメリットがあります。
・督促の停止
受任通知が債権者に届くと、原則として債権者は依頼者への電話や手紙での督促を停止します。これにより、依頼者は精神的な負担を軽減でき、冷静に借金問題に取り組むことができます。
・借金問題の整理
受任通知によって督促が止まると、司法書士が依頼者の債務整理を進めるための準備を始めることができます。これにより、今後の返済計画を立て、整理を進めていくことができます。
・法律的な保護
受任通知は、借金問題における法的な保護を依頼者に提供します。債権者が不当な方法で督促を続けることを防ぐため、法的な対応をしっかりと進めることができます。
3. 受任通知後の対応
受任通知が送られた後、債権者との交渉が本格的に始まります。依頼者が希望する返済方法や、借金の減額・免除を求める交渉が行われることが多いです。司法書士は、依頼者の立場に立ち、最適な解決方法を模索していきます。必要に応じて、任意整理や個人再生、自己破産など、最も適切な方法を選択して対応します。
借金問題に関して不安や悩みがある方は、まずは専門家に相談することをおすすめします。問題解決に向けて、まずはお気軽にご相談ください。
知っておきたい「受任通知」の注意点

受任通知は、弁護士や司法書士が債務整理の依頼を受けた際に、債権者に対して「債務者を代理することを正式に受任した」と通知する重要な文書です。
この通知が届くことで、貸金業者や債権回収会社(サービサー)など一部の債権者については、法律により債務者への直接的な取立てや連絡が禁止され、今後のやり取りは代理人を通じて行うことが求められます。
通常の場合、受任契約後、1週間程度で督促が止まります。
ただし、銀行や個人債権者等には法的な強制力はなく、実務上は代理人を通じた対応となることが多いですが、必ずしも全ての債権者がこのルールに従うとは限りません。そこで、受任通知について知っておくべき注意点がいくつかあります。
[銀行口座が凍結される]
銀行からの借入がある場合、債務整理の受任通知が銀行に届くと、銀行預金口座が凍結されることがあります。これは、銀行が債権者として「相殺」や「担保権行使」の措置を取るためです。
必ず凍結されるわけではありませんが、給与振込や公共料金の引き落とし口座は事前に変更しておくことが望ましいです。
特に、銀行口座に給与振込や公共料金の引き落としなどの定期的な入出金が行われている場合、受任通知後に口座が凍結されると、残高や給与が受け取れなくなったり、公共料金の支払いが滞ったりする恐れがあります。そのため、債務整理を始める前に、事前に給与の振込先や公共料金の引き落とし口座を変更する手続きを行っておくことが重要です。
[信用情報機関に登録される]
「受任通知が届いた=即信用情報登録」ではなく、債務整理の開始が登録理由となります。
債務整理の手続きが開始されると、その事実が金融機関等を通じて信用情報機関(CIC、JICC等)に「事故情報」として登録されます。これにより、信用情報に登録された「事故情報」、いわゆる「ブラックリスト」は一定期間(通常は5〜10年程度)保持され、その間は新規のクレジットカード申請やローンの審査において利用が制限されることがあります。
債務整理を行った場合、金融機関や貸金業者が新たに信用を供与する際に慎重になるため、クレジットカードや住宅ローンなど、ローンの申請が難しくなることがあります。特に、消費者金融や銀行などが提供するローンやクレジットカードは、この情報に基づいて審査を行うため、受任通知後の一定期間は利用が制限されることを理解しておく必要があります。
[借金の保証人に請求がいく]
債務に保証人、特に連帯保証人がついている場合、債務整理の受任通知が届くと、債権者は債務者本人だけでなく保証人にも請求できます。保証人は引き続き法的責任を負うため、債務整理前に保証人へ説明し、理解を得ておくことが重要です。
[受任通知が通用しない業者もいる]
受任通知は通常、弁護士や司法書士が債務整理を行う際に、債務者を代理人として正式に受任したことを債権者に通知する重要な文書です。この通知を受けると、債権者は債務者本人に直接連絡することができなくなり、すべての対応が代理人を通じて行われることになります。しかし、例外的に受任通知が通用しない業者も存在します。
その代表的な例が、悪質なヤミ金業者や違法な貸金業者です。これらの業者は、法的な規制を無視した営業を行っていることが多く、受任通知を送付してもその内容を無視して、直接債務者に連絡を取る場合があります。特にヤミ金業者は、暴力的な手法や脅迫を用いて債務者に対する取立てを行うことがあるため、受任通知が届いてもその後の対応が困難になることがあります。
こうした業者に対しては、受任通知を送っただけでは効果が薄いことがあるため、弁護士や司法書士と連携して、法的手段を講じることが重要です。たとえば、警察への相談や、裁判所を通じた強制的な対応を行うことが必要になる場合があります。受任通知が通用しない業者に対しては、さらに強力な法的措置を取ることを検討する必要があります。
受任通知を「受け取ったら」どうなる?考えられるリスクと影響

受任通知は、弁護士や司法書士が債務整理を担当する際に、債権者に対して債務者を代理する旨を通知する重要な文書です。この通知が届くと、貸金業者や債権回収会社(サービサー)など一部の債権者については、法律により債務者への直接的な取立てや連絡が禁止され、今後のやり取りは代理人を通じて行うことが求められます。一般の債権者(個人や通常の事業者など)には法的な強制力はありませんが、多くの場合、代理人を通じた対応となるのが実務上の慣行です。
しかし、「どこかから『受任通知』が届いた」「発送元が弁護士や債権回収会社になっている」など、受任通知を「受け取る」こともあるかもしれません。これは、どのような状況なのでしょうか?受任通知が「自分に届いた」場合について、詳しく解説します。
法律事務所や債権回収会社から「受任通知」が届くとは?
債権回収の過程で、法律事務所から「受任通知」が送られてくることがあります。受任通知は、委任された弁護士や司法書士が債務者の代理人として債権者に通知する文書であり、債務者と債権者との直接的なやり取りを控え、今後の対応は代理人を通じて行うよう伝えるものです。この通知が送られてくる場面には、いくつかのケースがあります。
1.支払いが滞った場合(延滞・未払い)
借入金や支払いが滞ると、取引先である債権者は法的手段を検討することがあります。最初は催促の電話や手紙が届くことが一般的ですが、支払いが続かない場合、債権回収の専門会社や法律事務所に依頼され、代理人から受任通知が送られることが多いです。この段階で債務整理や返済計画の再交渉が始まることもあります。
2.債権回収会社が関与した場合
多くの企業や金融機関は、債権回収が難航すると、専門の債権回収会社に債権の回収を委託することがあります。この場合、債権回収会社が債務者に対して「債権回収委託通知」や「債権譲渡通知」などを送ることはありますが、「受任通知」は通常、弁護士や司法書士が代理人として送る文書です。債権回収会社は、債務者に対して取立てを行い、財産を調査するなど必要に応じて法的手段(民事での訴訟や強制執行)を講じることがあります。
3.担保が設定されている場合
住宅ローンや借入契約に担保が設定されている場合、債務者が返済を滞納すると、担保権を行使するために法律事務所が介入し、受任通知が送られることがあります。この場合、担保に関する処理が行われることになりますが、債務者が返済をしない場合、最終的には自宅の差し押さえなど強制執行に進むこともあります。
受任通知は、主に債務整理や債権回収の過程で代理人(弁護士や司法書士)が関与した場合に送られる文書です。債権回収の専門家が関与した場合には、受任通知が送られることが多いため、通知が届いた際には早急に対応することが大切です。
「受任通知」を無視したらどうなる?起こりうる最悪のケース
受任通知が届いた場合、無視することは極めて危険です。受任通知は、貸金業者や債権回収会社(サービサー)に対し、債務者への直接取り立てを禁止する法的効力を持つ文書です。ただし、一般の個人債権者には強制力がありません。無視するとそれぞれ次のようなリスクが発生します。
1. 債権回収手続きの加速
裁判所を通じて民事訴訟が開始されます。もし敗訴した場合、訴訟費用として約10万円が追加で発生することになります。一方、支払督促が届いた場合、異議を申し立てなければ、2週間以内に強制執行が可能となります。異議を申し立てなければ、法的措置が進行するため、速やかに対応することが重要です。
2. 強制執行のリスク
差し押さえの対象となる財産は、給与(原則として1/4まで)、預金口座、不動産などです。しかし、例外として、生活保護費や99万円以下の現金は差し押さえが免除されます。
3. 債務の膨張
遅延損害金として法定金利(年14.6%)または契約金利のいずれか低い方が適用され、元金に加算されます。
4. 信用情報への登録
強制執行や破産手続きの記録は「JICC」「CIC」に5~10年間残り、ローンやクレジットカードの利用が不可能になります。
5. 破産手続きの可能性
免責の要件については、破産申立てを行った後、裁判所による審査を受けた結果、債務が免除されます。しかし、浪費や詐欺行為などがある場合には、免責を受けることができません。また、職業制限に関しては、弁護士や公認会計士といった一部の職業は、破産手続きにより資格を失うことになります。
受任通知が届いた際に無視することは、非常にリスクが高い行為です。無視を続けることで法的手続きが加速し、最終的には差し押さえや破産手続きに進展することになります。受任通知が届いた時点で、迅速に専門家に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
受任通知が届いたときにすぐ確認すべきポイントと対応法
債権回収を目的とした通知が届いた場合、まずはその内容を正確に把握することが重要です。通知の内容や対応方法を誤ってしまうと、さらに問題が悪化する可能性があります。特に、通知が債権者からの正式なものである場合、迅速かつ適切に対応しないと、法的手続きが進行してしまうことがあります。
1. 通知の内容を確認する
まず最初に、届いた通知の内容をよく確認しましょう。以下の点を確認することが大切です。
・通知の送付元:債権者やその代理人(弁護士や司法書士)からの正式な通知かどうかを確認します。
・債権の詳細:通知に記載されている金額や、債務の内容、支払期日などを確認します。
・通知の種類:警告通知や最終通告、法的手続きに関する案内など、通知の種類によって対応方法が異なります。
2. 通知を無視しないこと
通知を受け取った場合、無視することは絶対に避けましょう。無視していると、債権者が法的手続きを進める原因になります。裁判を起こされたり、強制執行が始まる可能性があるため、早期に適切な対応をすることが大切です。
3. まずは相談する
通知を受け取ったら、すぐに専門家に相談することをお勧めします。司法書士や弁護士に相談することで、以下のことがスムーズに進みます。
・債務整理の選択肢:債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を考える場合、専門家が最適な方法を提案してくれます。
・交渉代行:債権者と直接交渉することが難しい場合、専門家が窓口となり、代わりに交渉を行います。
・法的手続きの防止:債権回収のための法的手続きが進行しないよう、事前に対応方法を考えます。
4. 返済計画の立て直し
債権者との話し合いや専門家の助言を受けて、返済計画を見直すことができます。返済が難しい場合、以下の方法で調整が可能です。
・分割払いの交渉:一括での返済が難しい場合、分割払いの交渉を行い、負担を軽減できます。
・金利の減額:交渉によって金利を減らすことができれば、返済の総額を減らすことができます。
・債務の減額や免除:場合によっては、債務の一部免除を受けることができることもあります。
5. 必要な書類の整理
通知に対して正式に対応するためには、必要な書類を整理しておくことが重要です。例えば、借入契約書や過去の支払い履歴、収入証明書など、債務の状況を示す書類を準備しておきましょう。これらの書類が、交渉や法的手続きにおいて重要な役割を果たします。
債権回収の通知が届いた場合、まずは通知の内容をよく確認し、専門家に相談することが最も重要です。特に、すでに滞納がある場合は無視せず、早く適切な対応を取ることで、法的手続きの進行を防ぎ、最適な解決策を見つけることができます。一方で、身に覚えがない場合、詐欺の可能性も否定できません。このように、自身で判断に困るような場合も、専門家への相談をおすすめします。司法書士や弁護士は、あなたの状況に最適なアドバイスを提供し、手続きの進行をサポートしてくれますので、安心して相談してください。
まとめ

受任通知は、司法書士や弁護士が債務整理の手続きを依頼された際に、債権者に対して「債務者を代理することを正式に受任した」と通知する重要な文書です。受任通知が届くことで、債務者と債権者との直接的なやり取りが一時的に停止し、すべての連絡は司法書士や弁護士を通じて行われることになります。これにより、債務者の負担が軽減され、適切な手続きが進められることが期待されます。
1. 受任通知の効力
受任通知には、以下のような効力があります。
・債権者との直接的な連絡停止:受任通知が送付されると、債権者は債務者に対して直接の連絡や取り立てを行うことができなくなります。すべての連絡は、司法書士または弁護士を通じて行われます。
・取立ての一時停止:受任通知により、債務者への取り立てが一時的に止まります。これにより、債務者は精神的な負担を軽減し、冷静に手続を進めることができます。
・交渉の場としての役割:受任通知が送られた後、司法書士や弁護士は債権者と交渉を行い、支払い計画の調整や、場合によっては債務の減額を目指します。
2. 受任通知の注意点
受任通知は強い効力を持つ一方で、注意点もいくつかあります。以下の点に留意することが重要です。
・全ての業者に効力があるわけではない:特に悪質なヤミ金業者や一部の違法な貸金業者に対しては、受任通知が無視されることがあります。こうした業者に対しては、受任通知だけではなく、法的手段を取る必要があります。
・支払いの遅れによる影響:受任通知が届いた後も、債務者が支払いを行わなければ、法的手続が進む場合があります。司法書士や弁護士は、交渉や調整を行うものの、最終的には法的措置を取ることもあるため、適切に指示を守ることが大切です。
・受任通知送付後の対応:受任通知が送られた後も、債権者から再度連絡が来ることがある場合があります。もし債権者から連絡があった場合は、早めに司法書士や弁護士に報告し、対応を相談しましょう。
・業者との連絡先の確認:受任通知が送付された業者の情報を確認し、対応漏れや誤送付がないように注意することも重要です。特に、同じ債権を持つ複数の業者がある場合、受任通知が確実に全ての債権者に届いていることを確認する必要があります。
3. 専門家に依頼するメリット
専門家に依頼することで得られるメリットも多いです。
・精神的負担の軽減:債務者は債権者からの直接的な取り立てを避けることができ、心理的に楽になります。司法書士や弁護士が間に入ることで、安心して手続きを進められます。
・交渉の代行:司法書士や弁護士が債権者と交渉を行い、最適な解決策を見つけるため、債務者は自分一人で交渉する必要がなくなります。
・法的手続きの開始:受任通知を送ることで、債務整理や個人再生、自己破産など、法的な手続きが正式に開始されることとなり、適正な手続きが進行します。
債務整理を依頼し、継続する頻繁な取り立てや督促から解放されると、平穏で落ち着いた気持ちで生活の立て直しをすることができます。アヴァンス法務事務所では現在、東京や大阪のみならず、全国から電話やメールで24時間、無料相談を受付しています。金融会社の督促や取り立てに大きなストレスを抱える前に、アヴァンス法務事務所にご相談ください。